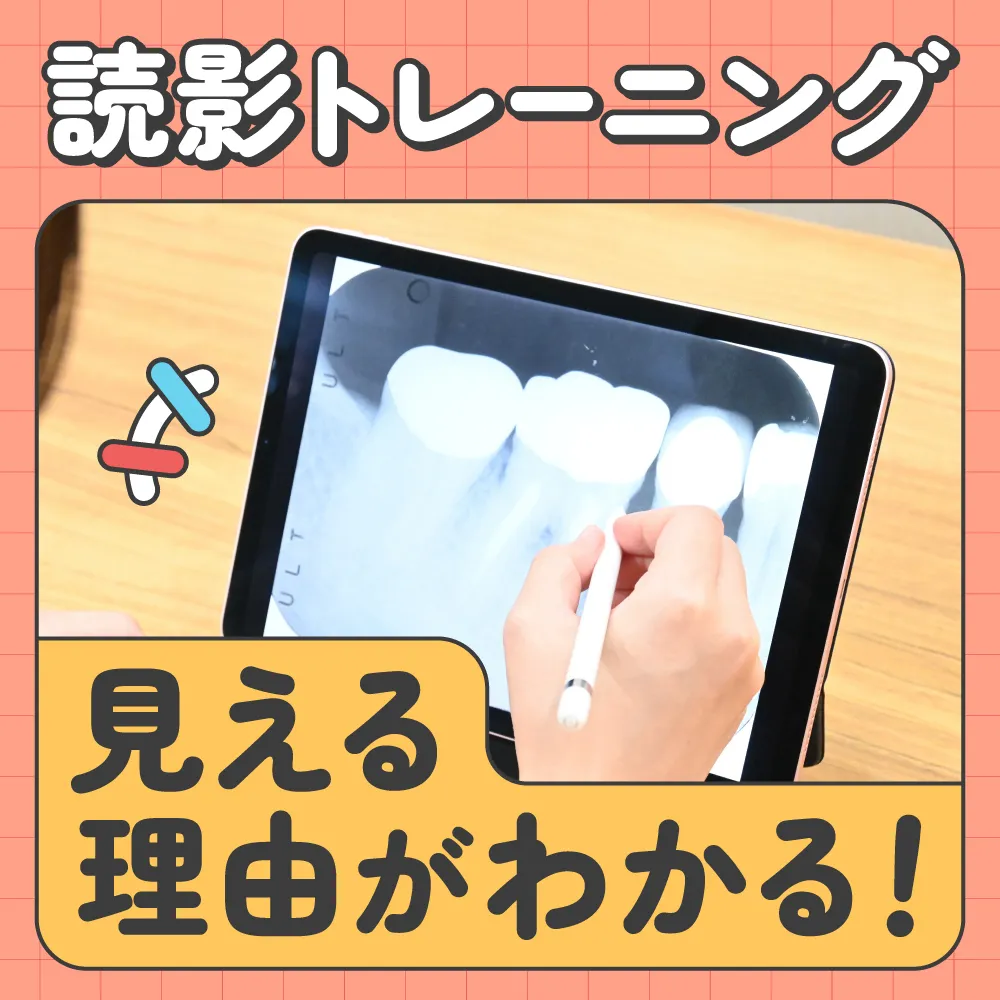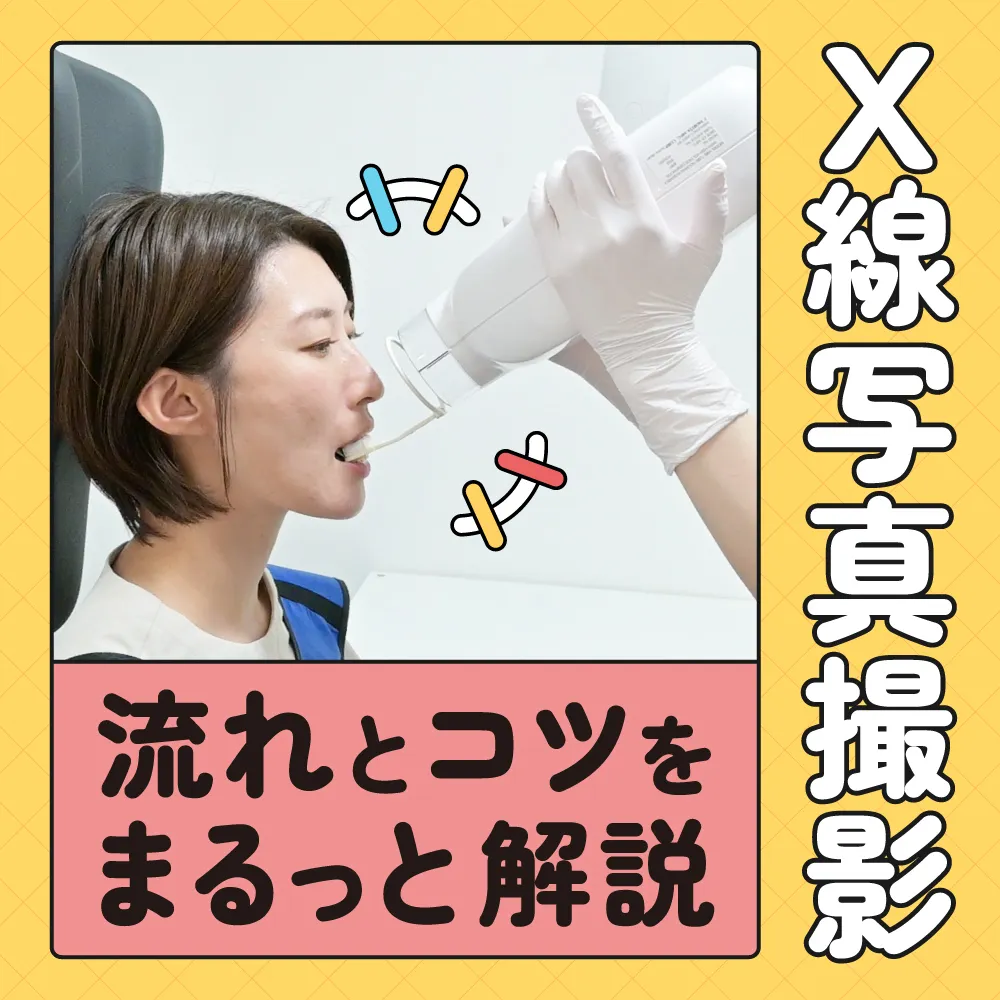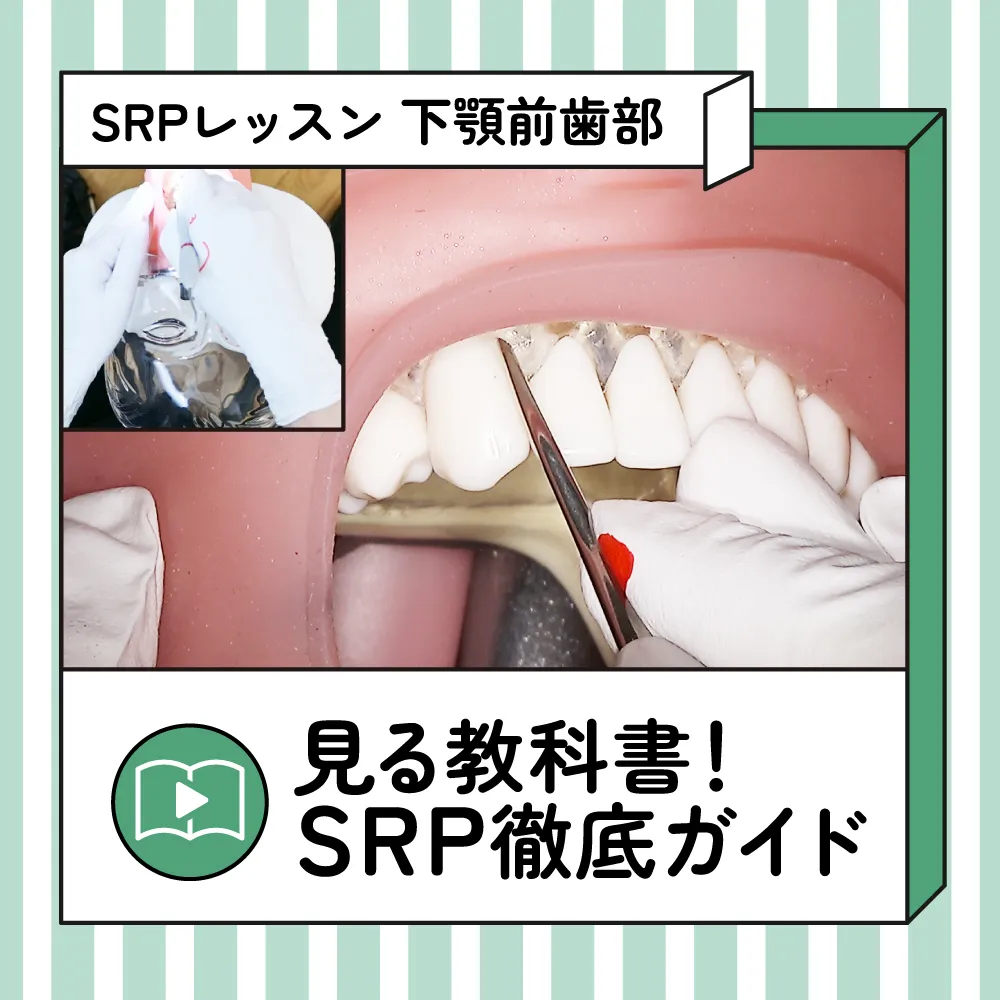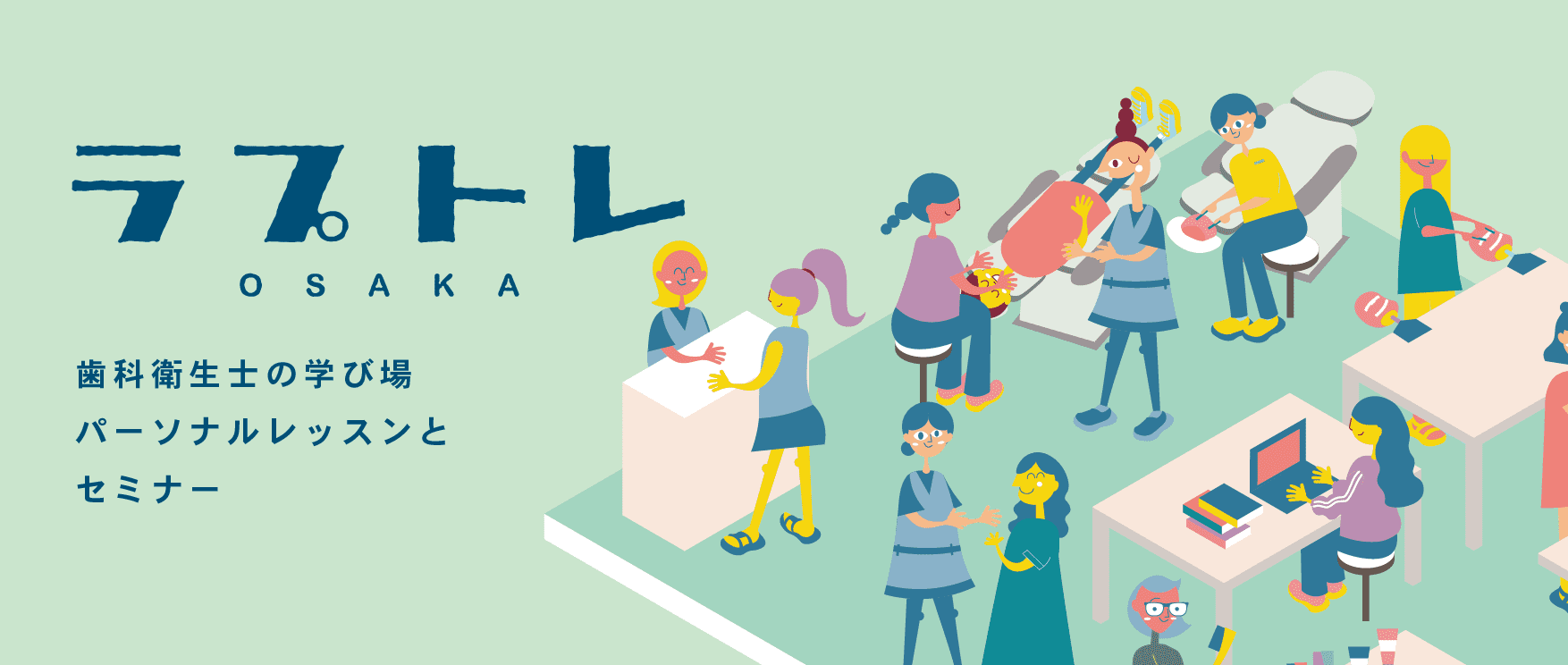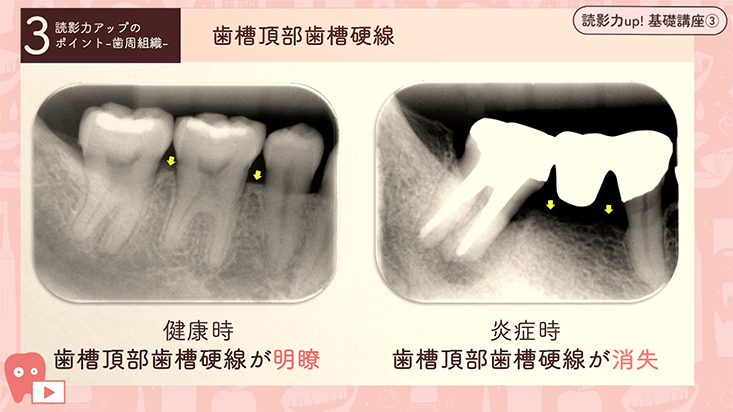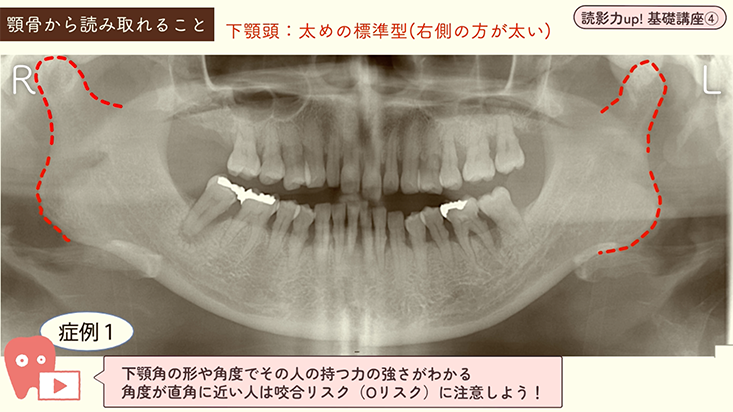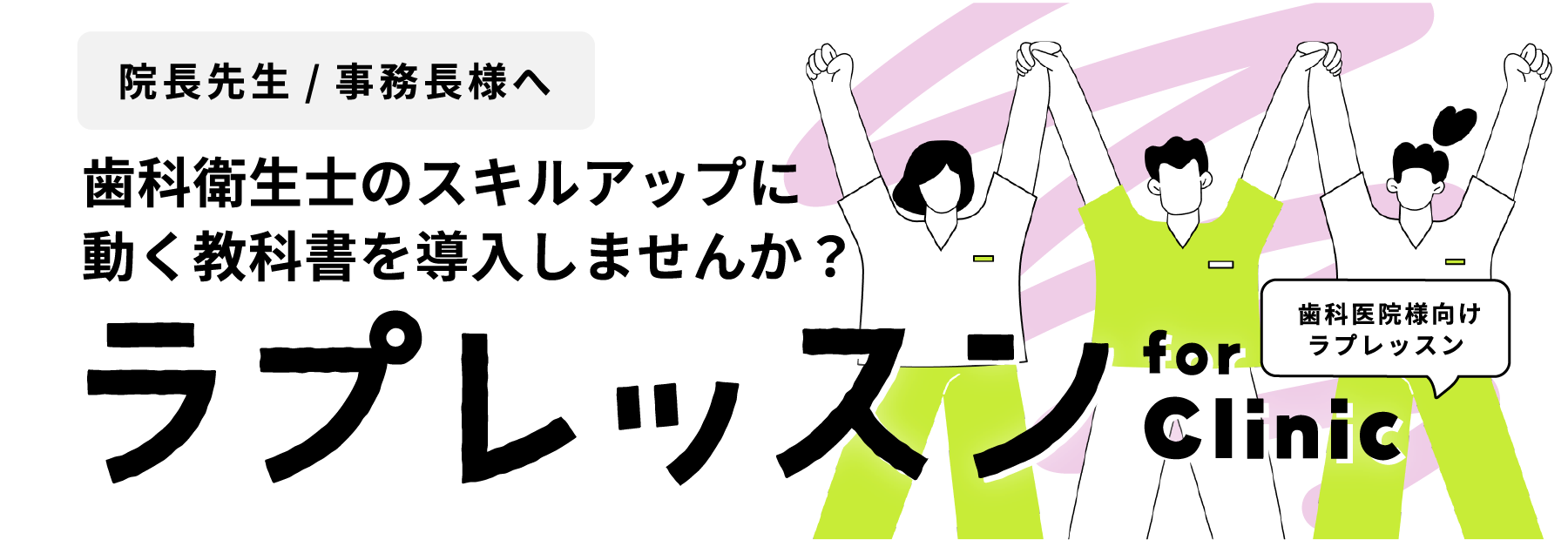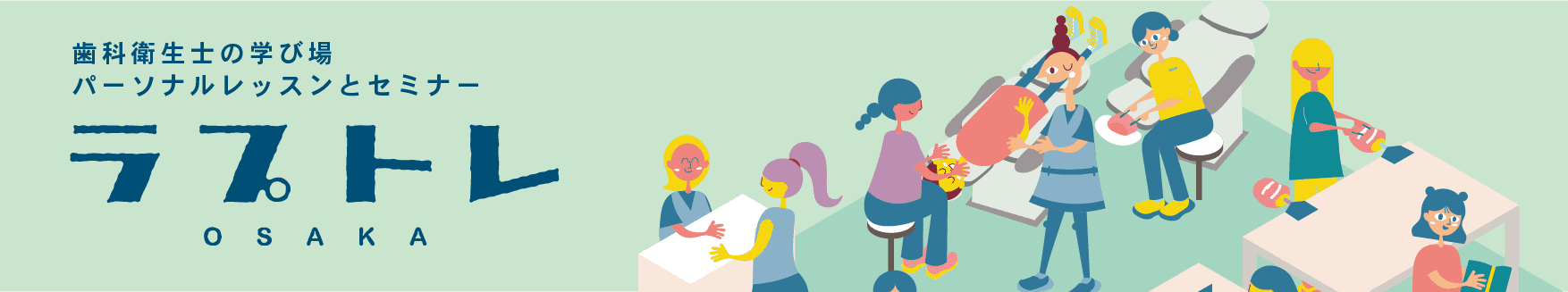読影力up!基礎講座
02.読影力アップのためのポイント-歯編-
この動画について
・治療歯・欠損歯を観る
・カリエスを観る
・カリエスと間違えやすい像
・コアの長さと太さを観る
・補綴物のマージン状態を知る
・根の長さと形態を観る
・根の湾曲と傾斜を観る
・歯冠ー歯根比を観る
・根の近接の程度を観る
・ルートトランクの長さを観る
・カリエスを観る
・カリエスと間違えやすい像
・コアの長さと太さを観る
・補綴物のマージン状態を知る
・根の長さと形態を観る
・根の湾曲と傾斜を観る
・歯冠ー歯根比を観る
・根の近接の程度を観る
・ルートトランクの長さを観る